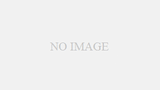春になると動物病院では予防のシーズン到来ということで、狂犬病にワクチン、ノミ・ダニにフィラリアといった様々な感染症に対する予防を目的に来院するワンちゃんネコちゃんが増える時期ですね!
そして病院内の色んな所から「〇〇の予防って必要ですか?」という質問が飛びかう時期でもあります。
今回はその中から『狂犬病』に関してお話ししたいと思います!
ちなみに狂犬病の予防注射は義務なので、毎年しっかりと受けさせてあげてくださいね!
狂犬病とは?
皆さん、狂犬病ってどんな病気かご存知ですか?
「自治体から注射案内のハガキが来るから予防はしてるけど、どんな病気か詳しくは知らないや」って方、多いんじゃないでしょうか。
実は私も子供の頃は、水を怖がるようになる病気で、毎年おじいちゃんが集合注射に連れて行ってるやつ!くらいにしか思っていませんでした。
狂犬病(rabies)は、哺乳類や鳥類という全ての温血動物が感染する人獣共通感染症で、発症すると限りなく100%に近い確率で死に至る病気です。
つまり、犬だけでなく人間にも感染する病気で、治療法がない為に発症するとほぼ死が待っている恐ろしい病気です。
厚生労働省のHPによると、日本、英国、オーストラリア、ニュージーランド、スカンジナビア半島の国々など一部の地域を除いて、全世界に分布しており、毎年5万5000人もの人々が狂犬病により亡くなっています。
感染経路は?
感染経路として代表的なのは、狂犬病にかかった動物に咬まれることで、その動物の唾液に含まれる狂犬病ウイルスが体内に侵入します。
アジア圏における狂犬病の感染にはイヌによる咬傷が大部分を占めます。
ヨーロッパやアメリカではワクチンや野犬対策によって犬の狂犬病は減少しましたが、キツネやタヌキ、アライグマやスカンクといった野生動物の間では流行が続いています。また、ヒトへの感染はコウモリ由来するものも多く、中にはコウモリに咬まれた記憶が無いのに発症するケースも出ています。
感染するとどうなるの?
日本で身近に狂犬病が存在したのは昔のこと…
今や狂犬病にかかった犬を実際に見たって方は殆どいないのではないでしょうか。
私も教科書や映像でしか見たことありません。
ここでは、狂犬病に感染したらどうなるのか、難しい言葉も出てきますが少し掘り下げてみようと思います。
狂犬病は大きく分けて潜伏期、前駆期、狂躁期、麻痺期の4つのステージに分けられます。
・潜伏期
咬まれる等により狂犬病ウイルスが体内に侵入し、末梢の神経から中枢神経、最終的には大脳へとウイルスがたどり着くまでの期間です。犬では21〜80日と報告されていますが、これは受傷した場所と脳までの距離や侵入したウイルスの数によって前後します。
・前駆期
ウイルスが大脳にたどり着く前後の期間で、この時期に発熱や倦怠感、食欲不振、悪心などの前駆症状がみられます。イヌではこの前駆期が半日〜3日間ほど続き、沈うつと活発な状態を繰り返します。
・狂躁期〜麻痺期
狂躁期になると、目的もなく歩き回り、目の前にあるものに咬みつくようになります。このため野犬の多い地域では多くのヒトや動物が咬まれ被害が大きくなります。
また、一般的に言われる水を怖がる症状ですが、これは本当に水が怖くなるのではなく、嚥下機能(飲み込む機能)が低下することで水をうまく飲めなくなることに起因します。ヒトでは咽頭部の筋肉が激痛とともに痙攣する為に水を怖がる様に見えるそうです。この時期を麻痺期と呼び、全身の麻痺症状による歩行困難などがみられます。そして、この麻痺期が数日続いた後、昏睡状態になり呼吸機能不全により死亡します。
狂躁期と麻痺期を明確に分けることは難しく、なかには狂躁期が無い麻痺型や沈うつ型も存在し、それらはヒトではコウモリ由来の狂犬病で多いとされています。
日本での発生状況は?
世界では毎年多数の死者が出ている狂犬病ですが、日本では1956年にヒトおよび犬、1957年に猫での発症が確認されて以来60年以上狂犬病は報告されていません。
しかし、1970年にネパールで犬に咬まれた日本人男性が1人、2006年にはフィリピンで犬に咬まれた日本人男性の2人が、いずれのケースも咬まれた後に無処置のまま帰国し発症しています。
これらは国外で狂犬病ウイルスに感染し、帰国後に発症しているので「輸入狂犬病」と呼ばれています。
このように、日本では狂犬病の発生が無くとも海外への旅行や出張が一般的になった現代では渡航先で感染するリスクがあります。その為、海外へ出掛ける際には狂犬病の発生状況を事前に把握し、現地では不用意に犬や野生動物に近づかないように心がける事が重要です。
狂犬病予防法と3つの義務
1950年に制定された狂犬病予防法には、こんな一文があります。
この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
この法律により、野犬対策や輸入時の検疫、予防接種が強化され、わずか数年で国内の狂犬病を封じ込めることに成功、現在まで60年以上国内での発生は確認されていません。
そんな狂犬病予防法ですが、飼い主への3つの義務が定められているのをご存知ですか?
【飼い主への3つの義務】
1.犬を飼い始めてから30日以内に市町村もしくは保健所への登録すること
2.狂犬病予防注射を年に1回必ず受けさせること
3.登録済みの証としての鑑札と狂犬病予防注射の済票を飼い犬に装着すること
これらの義務は生後91日以上の犬から適応されます。
義務を守らなかった場合、20万円以下の罰金が科されることもあり、警察庁によると2016年度の検挙数は223件だったようです。
国内での発生および感染拡大を防ぐために出来ること
現在の日本における狂犬病予防注射の接種率は約7割と言われています。
これは、“集団内の免疫が70〜75%を超えていればその集団内で伝染病は流行しない”というシャルル・ニコルの法則を満たしており、もし国内で狂犬病が発生したとしても流行することはまず無いと考えられます。
しかし、この接種率7割という数字は、市町村や保健所に登録されている犬の総数と予防注射を受けた犬の数で求められている為、登録されていない犬の数は含まれていません。
つまり、登録されていない犬を含めると接種率は大幅に低下します。
一説によると2014年度の接種率は45.9%、半数以下の犬しか狂犬病予防が出来ていない事になり、これでは流行を食い止められる保証はありません。
本当にここまで接種率が低いのかどうかは分かりませんが、飼い主1人ひとりが予防注射の重要性を認識し飼い犬に受けさせることで、仮に狂犬病が発生しても最低限の感染で抑えられる環境が作れるはずです。
さいごに
60年以上国内発生がない事で過去の病気と侮りがちですが、治療法の見つかっていない致死率100%の病気だということを再度認識し、年1回の狂犬病予防注射の必要性を感じていただければと思います。